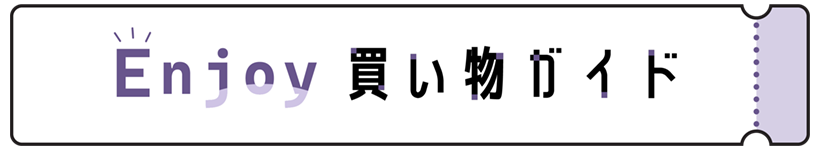デジタルギフトカードとは?

デジタルギフトカードは、オンライン上でやりとりできるギフト券のこと。
バーコード・QRコード・URL・メールなどのさまざまな形態があり、直接相手に会わなくても手軽にギフトを送れることが魅力です。
受け取った相手は、対象ショップでバーコードを見せたり、通販サイトでIDを入力したりすると、商品やギフトカードを受け取れます。
- Amazonギフト券
- Appleギフトカード
- ローソンソーシャルギフト
- サーティーワンeGift
Amazonギフト券やAppleギフトカードは、指定した金額分をプレゼントできることから、商品券のオンライン版だと言えますね。
ローソンソーシャルギフトやサーティーワンeGiftは、お金ではなく商品をプレゼントするもの。
ギフトコードを送ると、全国の店舗で指定した商品と引き換えられます。
デジタルギフトカード市場のシェア率は右肩上がり
デジタルギフトカードの市場規模は、ここ数年で大幅に成長しています。
日本だけでなく世界でも流通量が増加している傾向にあり、2020年は2,583億4,000万米ドルもの規模に到達しました。
2030年には1兆1,030億3,000万米ドル規模になると予測されていることからも、急速に成長している市場であることが分かります。
(参照:PR TIMES)
現在は、北米エリアでのシェア率が高め。日本をはじめとするアジア太平洋エリアでは、今後さらにデジタルギフトカード市場が拡大していくと予想されています。
デジタルギフトカードの種類
需要拡大に伴って、デジタルギフトカードの種類も多様になりつつあります。
登場初期は、Amazonギフト券などの商品券に近いものが一般的でした。
しかし現在は、飲食店の商品引換券やファッション専門店、コンビニなど、手軽に送れるギフトが増加傾向です。
新規顧客獲得の戦略としてもデジタルギフトカードが利用されていて、エンターテイメント事業や福祉業界までも浸透しています。
人気の理由

では、なぜデジタルギフトカードの需要が急増しているのでしょうか?
以下の要因が、デジタルギフトカード市場の成長に大きく影響していると考えられています。
- スマートフォンの普及
- コード決済に対する認知度の高まり
- 新型コロナウイルスによる電子会計の普及
- 手数料や送料が発生しない
スマートフォンの普及によって手軽にやりとりできることはもちろん、コード決済の認知度が高くなったことも大きな要因です。
また、新型コロナウイルスによる影響も。
非接触会計が推奨されたことによって、便利なデジタルギフトカードが広く利用されました。
店に買いに行ったり、直接渡しに行ったりする手間がないことはもちろん、手数料や送料が発生しないことも魅力の一つです。
\関連記事/
ギフトの在り方が変わっている?
デジタルギフトカードが普及する前は、お中元・お歳暮・結婚祝いといった大きなイベントのときのみ贈り物をすることが一般的でした。
しかし、デジタルギフトの登場によって、現在は手軽で簡単なプレゼントが増加しています。
- お世話になった人へのちょっとしたお礼
- いい商品を友達におすすめしたい
- 頑張っている家族にプレゼント
- 住所が分からない友達へ誕生日プレゼント

日常でのささやかなプレゼントとして利用されることが多く、イベント起点からカジュアルなプレゼントへと年々変化しています。
関わる人とのコミュニケーションツールとしても、手軽なデジタルギフトを活用する方が多いです。