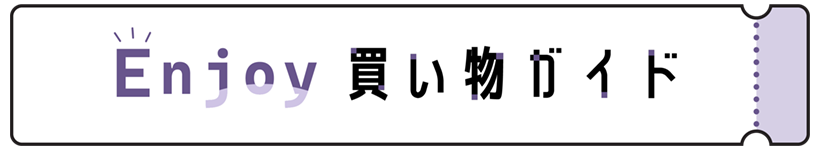地域振興券とは?

地域振興券(ちいきしんこうけん)は、1999年4月1日から9月30日の間に配布された商品券のことです。
当時の緊急経済対策として、15歳以下の子供と年金受給者を対象に、一人あたり2万円分が発行されました。

1,000円×20枚つづりのお釣りが出ない商品券で、有効期間は交付日から6ヶ月です。
約7,700億円もの財源はすべて国が負担しており、日本全国にある自治体によって対象国民に交付されています。
市町村ごとにデザインが異なる
配布に関しては地方自治体が主体となって行ったため、地域別にデザインを変えることができました。
たとえば、地元出身の漫画家がいる鳥取県東伯郡大栄町では、「名探偵コナン」の絵柄が書かれた地域振興券が配布されています。
個性的なデザインの地域では、地域振興券自体が人気になってしまい、転売が行われた事例も少なくはありません。
地域振興券の配布対象
地域振興券の配布対象は、下記の通りです。
- 1999年1月1日時点で15歳以下の子供
- 老齢福祉年金受給中かつ満65歳以上の高齢者
条件を満たす全国民に配布されたことから、対象者の合計は3,509万人にものぼりました。
地域振興券の目的
地域振興券が配布された目的は、「落ち込んだ消費を喚起すること」と「地域経済の活性化」です。
各自治体で経済を回すために、利用範囲は発行元の市区町村内のみに限られます。
当初は全国民に配布する案が出ていましたが、予算の都合上、対象者が絞られることになりました。
そのため、子育て支援が必要な世帯や所得が低い高齢者のみに配布されています。
地域振興券の効果
多くの人が地域振興券を使用することで消費量が増加し、一時的に経済が活性化されました。
しかし、地域振興券によって使わずに済んだ現金を貯蓄に回すことで、結果的に消費量が変わらない家計も少なくはありません。

経済企画庁が行った調査では、使用額の70%前後が貯蓄や日常消費に回されてしまったことが分かり、期待したほどの消費喚起の効果はありませんでした。
交付された世帯に関する消費の押し上げ効果は、発行した額の10%程度とも言われています。
そのため、地域振興券が直接景気回復に結びついた、と明確には断定できません。
地域振興券の変遷
1999年に配布された地域振興券ですが、現在では政府や自治体が発行するクーポン全般を指す言葉として使われることがあります。
国民に向けて地方自治体が発行してきたクーポン・商品券・現金配布の変遷をみてみましょう。
2008年のリーマンショックによる影響を受けたことによる経済対策として、一律1万2,000円が配布されました。
※18歳以下と65歳以上の高齢者は、一人あたり2万円
全国民を対象としたことにより、約2兆円もの国費から賄われています。
1999年の地域振興券施策と比べると、かなり大規模な経済対策であることが特徴です。
緊急経済対策として打ち出された施策であることから、所得や年齢の制限を設けずに一律で現金が配布されました。
2015年には、日本全国の市区町村が発行するプレミアム商品券が販売されました。
地域活性化のために行われた取り組みで、購入額に対して一定額を上乗せした金額分の買い物ができます。
発行した地域のみで利用できる商品券となっており、地元限定商品のみが購入できるものなど幅広い種類があります。
消費税引き上げで経済が落ち込んだ2019年には、プレミアム付商品券として、再度販売されています。
まとめ
1999年に発行された地域振興券は、現在行政が発行するクーポン券全般を指す単語として使われています。
さまざまな理由によって落ち込んだ経済を活性化するために、数年おきにクーポン券を利用した経済対策が行われています。
今後も地域振興券のような施策が行われる可能性があるので、対象者になったときは積極的に利用しましょう。